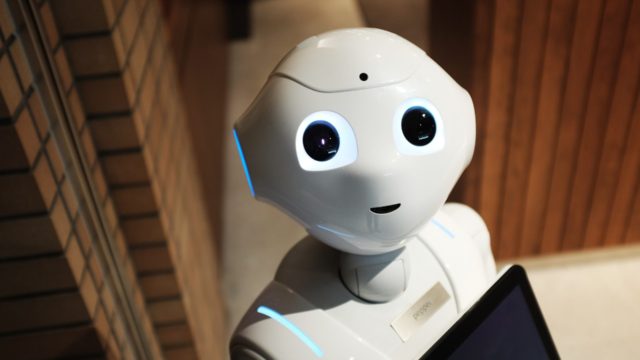死んだ彼女の葬儀に行った日のことと「生きる」ということ
「桑(僕)は、あのあと誰とも連絡取ってないでしょ。アメリカにいるって噂はあったけど、どうしてたの?」
「生きてたよ…」
地元の同級生と16年振りに言葉を交わした。
「ああ、俺がアメリカにいるって話は広まってたんだ」と思った。
「あのあと」とは、僕が高校を卒業した年の10月10日のこと。
今まで生きていて、最も忘れることができない日のあとのこと。
その前日、親友のIから僕に電話があった。
彼に、卒業した高校の元担任Mから電話があった、と伝えられ、
「俺が今から言うことを落ちついて聞いてくれ。頼むから落ち着いて聞いてほしい」
と言われた瞬間、彼が次に何を言うのか、僕にはわかった。
「Nが…死んだ。今日病院で亡くなって、明日、室蘭で葬儀がある」
心のどこかで予期していた。
それでも、「そのとき」が来たときの衝撃は大きすぎた。
身体の震えが止まらなかった。直後に彼に何と言ったかは覚えていない。
ただ、意識が遠のいていくほどの心拍数の乱れと、電話を持てなくなるほどの震えだけは、ずっと鮮明に覚えている。
人生で唯一付き合った女性の死を、「落ち着いて聞いてくれ。」
全く同じ日に生まれた彼女の死を、「落ち着いて聞いてくれ。」
こんなのを落ち着いて聞けるやつなんて、それこそ頭がどうかしてる。
「桑、聞いてるか?大丈夫か?」
「ああ…。大丈夫かどうかは知らんけど、聞いてはいる」
彼は通夜や葬儀の日時を僕に伝え、僕と二人で参列するアレンジを始めた。
「俺が車で迎えにいく。この間、兄貴ん家行ったときと同じ場所で待ち合わせしよう」
「いや…。俺、行かないよ」
「ん?どういうこと?葬式に行かないってことか?」
「行かないよ。何で…俺が行くんだよ…」
「おい!何考えてんだ!おまえが行かなくてどうすんだ!」
彼は突然怒り出した。
彼女が白血病になってから別れを切り出されたとは言え、僕が彼女のことをどのように思っていたか、彼にずっと打ち明けてきた苦悩の数々を考えれば、怒られるのは当然のことだ。
彼の怒りは、今になってよくわかる。
「どうもなんねーよ!行かなくても、どうにもならねーよ!」
でも、錯乱状態に陥るのを必死で堪えていた僕には、物事を判断する力も、先のことを考える余裕もなかった。
そして、その後も、あまりにしつこく葬式に連れ出そうとするIに、僕も混乱を押さえきれずに怒り出した。
「行かねえっつってんだろ!行ったらどうなるんだ!?何が変わるんだ!?俺が行ったら生き返んのか!?生き返るんだったら何度だって行くよ!でも、そうじゃねえだろーがよ!!人の気も知らないで『葬式に来い』なんて簡単に言うな!!」
と言い出し、お互いに声を荒げて、電話口で少し喧嘩になった。
そして、押し問答の末に痺れを切らした彼は、「俺は明日、〇時に桑園駅の前におまえを迎えに行く!前と同じ場所で待ってるからな!絶対来い!」と言い残して、一方的に電話を切った。
電話を切ってしばらくは「ふざけんな、あの野郎!」と思ってたけど、段々と色々な感情がごちゃごちゃになって、その後、僕は何時間も机に突っ伏して泣き続けた。
彼女の遺体を見るのが怖かったのか。
みんなの前で正気を保っていられる自信がなかったのか。
「死んでから行っても遅い」と思っていたのか。
とにかく、僕は行きたくなかった。
それから何をしていたかは記憶がない。仕事に行って、泣きながら店長に休みをもらったこと以外は、どうしても思い出せない。
気がついたら、夜が明けていた。
次の朝、結局、僕はIとの待ち合わせ場所に行った。
「人の気も知らないで」なんて言ってしまったけど、彼女の白血病が発覚してから死ぬまでの僕の混乱を、彼は最も身近で見てきた人間だ。
次の日、指定された待ち合わせ場所でお互いを見ると、二人とも恥ずかしそうに手を振った。
「I、ごめん。昨日は俺が悪い」
「あんな桑は初めてだわ。おまえ、キレ過ぎだよ」
「おまえは人のこと言えないだろ…」
「ははは」
久しぶりに少しだけ笑って、僕の心が少し軽くなった。
あとは、いつもの調子で、札幌から室蘭まで二時間のドライブ。
途中で心の整理のために止まってもらったこと、思いがけない車の故障があったことで、結局、二人で葬儀に少し遅刻して参列した。
到着して最初に覚えているのは、高校のクラスメイトたちが好奇心で僕をジロジロと見ていたことだ。強い不快感を感じて、すぐに来たことを後悔した。
そして、葬儀の最後に棺に献花をするとき、二年半の長い白血病との闘病生活の末に、骨と皮になるまでやせ細った彼女の遺体を見た。
高校で3年間ずっと同じクラスだった彼女と、卒業して半年経って初めての対面。
棺の中で化粧をして横たわっていた彼女は、僕と付き合っていたときとは別人のようだった。
何で、こんな形で苦しまなきゃいけないんだ。こんなのは、おかしいだろ!
答えのない問いを、
誰が答えるわけでもない問いを、
僕は心の中で繰り返した。
全く同じ日に生まれたことを知って喜んだ瞬間、
入院が決まったときに電話してきた不安そうな彼女の声、
別れの手紙を共通の友人経由で渡されたときの自分の震える手、
もう二度と動くことのない彼女の前で、色々な記憶が鮮明に蘇ってくる。
彼女が白血病であることがわかってから、クラス替えの際には、学校側の露骨な配慮で、彼女の幼馴染、彼女と仲の良い人たち全員が、彼女と同じクラスに割り当てられた。
そして、なんの巡り合わせか、僕もその特殊なクラスの一員になった。
ただの偶然だと、当時は思っていた。でも、もしかしたら、彼女と一緒に過ごす時間が長かった僕を、学校側が意図的に同じクラスにしたのかもしれない。そう思わなくもないけど、今となっては、真相は誰にもわからない。
あのクラスになってよかったかと聞かれると、僕には答えがない。学校社会に生きる高校生にとって、教室は世界の大部分。たくさんの辛い物語が、そんな狭い空間で繰り返し起きてしまった。
別れを切り出す前の彼女の気持ちを考えられなかった、大事なことを言葉にして伝えなかった自分自身が、今でもときどき嫌になる。
僕はあまりにも状況を知らなすぎた。共通の友達だった彼女の幼なじみに、彼女が白血病であることを初めて伝えられた夜、泣きながら言われた言葉が胸に突き刺さった。
彼女の幼馴染は、誰一人、僕を責めなかった。それどころか、折に触れて、僕のことも気遣ってくれた。
だけど、悪いのは僕だ。情けなかったのは、誰でもない、僕自身だ。
あまりの障害と冷たい反応の多さに、すぐに諦めてベストを尽くさなかったのは、紛れもない僕自身だ。
彼女が死ぬのは止められない。けれども、最期の時を迎えるだろう人間に対して、僕にはできることが数多くあった。「死ぬとは思っていなかった」なんて言い訳は通用しない。
そう考えたとき、発狂しそうなほどの罪悪感と後悔が胸を締め付けた。
あの頃のことは、今でも夢に出てくる。あまりに何度も夢に出てきたので、自分に都合のいいバージョンの夢で、実際の記憶を書き換えようとさえ思った。
葬儀場には高校の同級生も沢山いて、僕のことをコソコソ話してる人もいたけど、僕はその場の誰とも口をきかずに、ご遺族以外の誰とも目を合わせないようにして、終わったらすぐにその場を去った。
それ以来、高校の友人・知人とは一切の連絡を絶った。
好きだった故郷を訪れることも止めた。
そして、自分の過去に重い蓋を閉めた。
この時期の数年の間は、色々なことがあった。
本当に、本当に、全てを記憶から消し去りたいくらい、色々なことがあった。
気が狂いそうになって親友に助けを求めたり、自殺未遂をしたり、1人で閉じこもってしまったり。
直面しなければいけない現実に、周りの心ない皮肉や噂話が加わったあのとき、子供だった僕は、精神の混乱や怒りをコントロールする術を、何ひとつ持ち合わせていなかった。
全く同じ日に生まれた2人のはずなのに、あの日を境に、僕だけが1人で年齢を重ね続ける。あの頃、僕の心はそれに耐える準備もできていなかった。
そして、それから何年も、何年も、心の奥でふさぎ込んでた。
後悔と罪悪感と怒りの狭間で、ただ苦しい日々を過ごしてた。
ようやく気持ちが少し落ち着き、アメリカから一時帰国した際に、Iに会いに室蘭を訪れることができたのは、それから7年が経った後だ。
そのとき、ふとIに聞いてみた。
「おまえさ、ほんとは、あのとき俺が自殺すると思った…?」
数秒の間を置いて、彼は言った。
「うん…」
だろうな。
何となく、そんな気がしてた。
だから、わざわざ遠くから迎えに来てくれたんだ。
だから、葬儀の後、「札幌に戻る」と言い張る僕を引き止めて、自宅に無理やり一泊させたんだ。
実際、彼がいなかったら、あの日、自分がどういう行動をとったか、あまり自信がない。彼女の遺体が焼かれている時間帯に、取り返しのつかないことをしていた気もする。
「あのときIが一緒にいてくれなかったら、俺はどうなってたんだろう」と、今でもときどき思う。
人は誰もが過去を抱えてる。
誰もが過去に影響を受けながら、自分なりの未来を描き、現在の行動を決めている。
人間とは、過去と現在と未来の3つの時間軸が、複雑に絡み合った存在だ。これらが交差する場所に、僕たちは今も生きている。
起こった過去をどう解釈して、どういう未来を想定して生きているかは、現在の一つ一つの選択に決定的な影響を与えている。
「生きる」とは、そのような交差点の真ん中で、「自分」を紡ぎだしていくことだ。
「アメリカにいるって噂はあったけど、どうしてたの?」
「生きてたよ…。Iって覚えてる?あいつには連絡してたよ」
「そっか…。桑も頑張ったんだ…」
「生きてた」
再会が急過ぎて、どんな言葉を返していいかわからなかったので、思わず出た言葉だったけど、そうやって表現するしかない歳月だったのかもしれない。
人は誰もが過去を抱えてる。
ときとして言葉にできないような想いに溢れた過去を。
それでも人は、過去と現在と未来が交差する「今」を生き、自分を紡ぎ出している。
「生きる」ことは簡単じゃない。その辺の人間がお気楽に考えるほど簡単じゃない。過去の解釈も、未来の方向設定も、現在の選択も。
気が狂いそうになるほどの痛みや苦しみを味わった若い人であれば、なおさらだ。
過去に死のうとした人が「生きる」ことに懸命になっているとき、自然に応援したくなる。自分の中の何かと強く共鳴して、心が自然に動く。
僕にできることはわずかしかない。でも、未来の選択肢を死をもって無にしようとする人がいれば、これからも自分にできることをしていきたい。
誰にも理解されなくても、僕はこれを続けていたい。